
運送会社やバス会社、タクシー会社へ就職・転職を検討している方のなかには、第二種免許の取得にかかる費用を詳しく知りたいと考えている方もいるでしょう。
この記事では、第二種免許の取得にかかる費用の紹介から、運転できる車両や、免許を必要とする仕事・必要としない仕事についても解説します。
さらに、第二種免許の取得にかかる時間や試験の流れ、合格するためのポイントも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
第二種免許にかかる費用の内訳

この章では、第二種免許の取得のために入校する自動車学校や教習所の料金や、試験時に必要な費用についてご紹介します。
入校や教習にかかる料金
第二種免許の取得のために、教習所に入校した際の料金は免許の種類によって下記のとおりです。
- 普通二種免許:20万円前後
- 中型二種免許:26万円前後
- 大型二種免許:17万~45万円程度(所持している免許によって異なる)
上記の料金は、平均的な金額ですので、教習所や合宿によって料金は異なる点に注意が必要です。
また、合宿で免許を取得する場合、シーズンによって費用が変動します。お得な時期だと4〜5万円程安く取得できることもあります。
さらに、教習所によっては初回の受講料が安くなるキャンペーンを実施している場合もあるため、利用予定の教習所のホームページの確認や直接問い合わせすることををおすすめします。
教習所だけでなく、第二種免許の資格取得支援がある会社もあるので、よりお得に免許を取得するなら就職するのも方法の1つです。
運送業に就職・転職をご検討中なら「ドラピタ」をご活用ください。ドラピタは運送業専門の転職・求人サイトなので、自分の希望に合った運送会社を見つけられます!
試験にかかる料金
教習終了後、試験場で本試験を受ける際に必要な費用は下記のとおりです。
- 試験申請:4,800円
- 試験車両:2,850円
- 応急処置講習:8,400円
- 応急教材費:3,300円
- 旅客車講習:18,600円
- 免許交付:2,050円
もし、教習所への入校はせずに一発試験にチャレンジする方は、上記の試験費用のみで抑えることが可能です。ただし、独学での試験は難易度が上がり、合格率も下がる可能性があるので注意しましょう。
第二種免許の基本

この章では、第二種免許にはどのような種類や運転できる車、必要とされる仕事について解説します。
第二種免許とは?普通免許との違いや種類
第二種免許とは、営業目的で旅客輸送をする場合に必要な免許です。第一種免許となる普通免許は、一般的な目的で公道を車で走るための免許であり、第二種免許は営業目的としていることに違いがあります。
第二種免許は、車両総重量、最大積載量、乗車定員などの条件によって区分があり、下記の5種類に分けられています。
| 免許の種類 | 車両総重量・最大積載量・乗車定員 | 代表的な車両 |
| 普通二種免許 | ・車両総重量3,500kg未満・最大積載量2,000kg未満・乗車定員10人以下の全てを満たす車 | ・タクシー・ハイヤー・介護送迎車など |
| 中型二種免許 | ・車両総重量7.5〜11t未満・最大積載量4.5〜6.5tkg未満・乗車定員11〜29人以下の全てを満たす車 | ・介護送迎バス・幼稚園の送り迎えの緑ナンバーのマイクロバスなど |
| 大型二種免許 | ・車両総重量11t以上・最大積載量6.5tkg以上・乗車定員30人以上の全てを満たす車 | ・路線バス・観光バスなど |
| 大型特殊二種免許 | フォークリフトやショベルカー、キャタピラー車、除雪自動車などの大型特殊自動車を運転して、旅客輸送事業を行う際に必要な免許 | 現時点で、大型特殊自動車を旅客輸送事業に使うという事例はない |
| けん引二種免許 | 大型トレーラーやタンクローリーなど荷台をけん引する自動車を運転して、旅客輸送事業を行う際に必要な免許 | 現時点で、旅客輸送に使う事例はない |
第二種免許が必要な仕事や不要なケース
第二種免許を必要とする仕事は主に下記のとおりです。
- 路線バス・高速バスの運転手
- タクシー・ハイヤー
- 貸切バスの運転手
- 介護タクシーの運転手
- 運転代行業
ただし、介護保険制度の適用となる「介護保険タクシー」の場合は、第二種運転免許に加えて、介護職員初任者研修を修了していることが条件となるので注意しましょう。
また、タクシーやバスを運転する場合でも、無料送迎や旅客を乗せていない回送、試運転、業務で従業員を乗せて運転する場合は、第一種免許で運転可能です。ほかにも、第二種運転免許を必要としないケースとして下記が挙げられます。
- 学校や幼稚園の送迎バス(有償や業務委託の場合は除く)運転手
- 工事現場のトラック運転手
- 引っ越し業者のトラック運転手
運転する内容によって異なるので、職場で必要な運転免許を確認しておきましょう。
第二種免許の取得条件
第二種免許の取得に必要な条件や、道路交通法改正による二種免許の受験資格の緩和ついて確認しておきましょう。
第二種免許の基本的な取得条件は下記のとおりです。
- 満21歳以上かつ他の二種免許を持っているか、一種免許の取得から3年以上であること
- 片眼で0.5以上かつ両目で0.8以上かつ、深視力が2cm以下であること
- 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること
ただし、運転免許の受験資格に関わる道路交通法が改正され、令和4年5月13日以降、19歳から中型・大型免許や二種免許の取得が可能になりました。
特例教習を受講することで、19歳以上、かつ普通免許等の免許期間が通算1年以上あれば、第二種免許の取得条件を満たせます。これにより、第二種免許の取得がしやすくなり、ドライバー人材の増加につながると考えられています。
第二種免許の講習時間・期間|学科が免除される所持免許

この章では実際に、第二種免許の取得に必要な講習時間や期間と、学科が免除される所持免許について、取得する免許の種類別でご紹介します。
ただし、大型特殊二種免許・けん引二種免許については、日本で必要な車両がない・西東京バスの限定バスのみで必要など、該当するケースがほとんどないため、今回の紹介からは除きます。
もし、最短で免許取得を目指したい方は、合宿への参加がおすすめです。合宿で取得する際の最短日数も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
普通二種免許
普通二種免許の取得に必要な教習時限は下記のとおりです。
| 所持免許 | 教習時限 |
| 普通免許 | ・技能教習21時限・学科教習19時限 |
| 大型・中型・準中型免 | ・技能教習18時限・学科教習19時限 |
合宿で取得する場合の最短日数の目安は、下記を参考にしてください。
- 普通免許所持:約11日
- 大型、中型、準中型免許所持:約7日~9日
合宿によってカリキュラムが異なるため、事前に確認しておきましょう。
中型二種免許
中型二種免許に必要な教習時限は下記のとおりです。
| 所持免許 | 教習時限 |
| 普通免許 | ・技能教習28時限・学科教習19時限 |
| 準中型免許 | ・技能教習24時限・学科教習19時限 |
| 大型・中型免許 | ・技能教習18時限・学科教習19時限 |
合宿で取得する場合の最短日数の目安は、下記を参考にしてください。
- 普通免許所持:約13日
- 準中型免許所持12日
- 大型、中型免許所持で約7日
こちらも、合宿先にカリキュラムを確認しておくとよいでしょう。
大型二種免許
大型二種免許の取得に必要な教習時限は下記のとおりです。
| 所持免許 | 教習時限 |
| 普通免許 | ・技能教習34時限・学科教習19時限 |
| 準中型免許 | ・技能教習30時限・学科教習19時限 |
| 中型免許 | ・技能教習24時限・学科教習19時限 |
| 大型免許 | ・技能教習18時限・学科教習19時限 |
合宿で取得する場合の最短日数の目安は、下記を参考にしてください。
- 普通免許所持:約16日
- 準中型免許所持:約15日
- 中型免許所持:約11日
- 大型免許所持:約7日
普通二種・中型二種と同様に合宿先で詳しい日数を確認しておきましょう。
第二種免許の試験の流れ
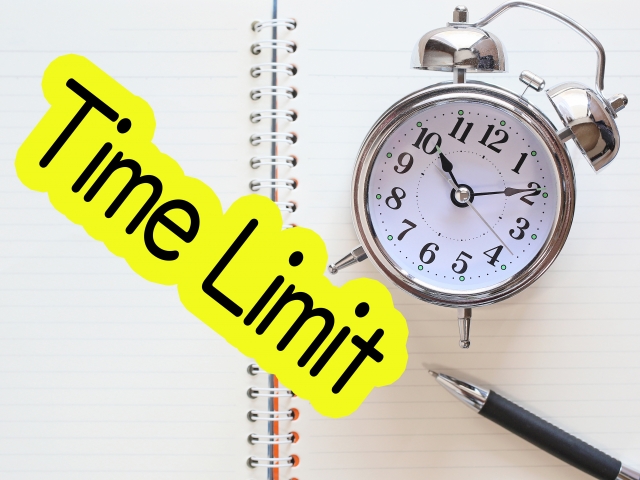
自動車学校・教習所で学科と実技の試験に合格したあとは、試験場で最終試験を受ける流れとなります。試験場での流れは下記のとおりです。
- 学科試験を受験して合格
- 実技試験を受験して合格
- 旅客車講習の受講
- 応急処置講習の受講
上記の流れを経て、免許の交付がされます。
学科と実技の試験の概要は下記の表を参考にしてください。
| 試験の種類 | 概要 |
| 学科試験 | ・マークシート形式で全95問・文章1問1点・イラスト1問2点・減点法で採点され、90点以上で合格 |
| 実技試験 | ・校内試験と路上試験、それぞれで合格する必要がある・減点法で両方とも90点以上で合格 |
第二種免許の取得は難しい?合格するためのポイント

第二種免許の取得は難しいのではないかと不安を感じている方に向けて、学科試験と実技試験の合格ポイントをご紹介します。
学科試験の合格ポイント
学科試験では、普通免許の試験と同じ内容と、それに加えて、第二種免許に必要な「旅客運送に関する問題」が出題されます。
試験項目では、配点が2点あるイラスト問題を注視しがちですが、基本的な問題を落とさないことが合格するためのポイントです。試験対策では、参考書やアプリの問題集などを活用して繰り返して問題を解くようにしましょう。
実技試験の合格ポイント
第二種免許の実技試験は、場内試験と路上試験の2つの試験に合格する必要があります。
場内試験では、縦列駐車、方向転換、鋭角コースの3つからランダムで2つのコースを受験します。鋭角コースはV字型のコースとなっており、第二種特有のコースです。切り返し1回でクリアする必要があるため、十分な練習をしておきましょう。
路上試験では、乗客を想定した本番と同じ運転の流れで採点されます。具体的には、指定コースの走行と停車、乗せるポイントへの停車、転回させる流れで進められるでしょう。停車位置の間違い、転回ミス、運転ミスに気をつけるのが合格のポイントです。
第二種免許の費用や取得について気になる質問

第二種免許の取得やかかる費用について、気になる質問を2つ厳選してご紹介します。
- 第二種免許を無料で取得できる方法はある?
- 第二種免許は廃止になるの?
それぞれの質問について詳しく見ていきましょう。
第二種免許を無料で取得できる方法はある?
第二種免許を無料で取得する方法はあります。会社によっては免許を取得するための支援制度を設けている場合があり、一部負担だけではなく、全額負担してくれる可能性もあるでしょう。
ただし、高額な費用を負担する代わりに一定期間の勤務や、途中退職の際の費用返還などの条件を設けている企業もあるので、事前に確認しておく必要があります。
第二種免許は廃止になるの?
現時点では、第二種免許は廃止されていません。しかし、2022年5月13日に道路交通法の改正で、受験資格の緩和が実施されています。また、2024年4月開始のライドシェアでは、二種免許を必須としないことも定められました。
日本では、ドライバー不足や地域の移動手段の確保のために、さまざまな政策や緩和を実施し始めています。ただし、特別講習の受講やタクシー会社での雇用などが条件になっているので、事前の確認が必要です。
第二種免許の費用は企業によって支援してくれる場合がある

第二種免許にかかる費用は、取得する免許の種類や取得方法によって異なります。費用を抑えて最短で免許を取得するなら、合宿がおすすめです。ただし、合宿免許への参加には、まとまった日数が必要になるので、ご注意ください。
また、第二種免許を必要とする仕事を確認しておくことも大切です。運転の内容によっては、第二種免許を必要としないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
ほかにも、企業によって第二種免許の取得費用を支援してくれる場合があります。
第二種免許の取得費用を支援してくれる就職・転職先をお探しなら「ドラピタ」にお任せください。
ドラピタは運送業専門の転職・求人サイトです。非公開求人も含めて、約3,000件の求人が掲載されているので、第二種免許の取得費用を支援してくれる会社がきっと見つかります。
運送業で幅広く求人情報を得たい方も、ぜひ「ドラピタ」を活用してみてください。


